家族や親族が亡くなった場合、49日までは自宅での供養や法要の準備など、しなければならないことが多くとても慌ただしいです。大切な人を亡くした悲しみに浸る間もなく、手続きや準備に追われ、心も体も疲弊することでしょう。
本記事では、49日までに起こることを、供養の流れとともに詳しく解説します。忌中にすべきことも詳しく紹介するので、49日までの流れとともにおさらいしておくと安心です。
49日までにすべきことが明確になるため、ぜひ参考にしてください。
目次
葬儀後から49日までの流れ

葬儀後から49日までの間はしなければならないことが多く、遺族にとっては慌ただしい時期です。ここからは、葬儀が終了してから49日までの流れについて、時系列を追いながら解説します。
葬儀後から1週間
葬儀から1週間を目処に、支払いなど葬儀の後処理を進めていきます。葬儀記録の整理やお世話になった人への挨拶も、早めにしておくと良いでしょう。
自宅には後飾り祭壇を設け、位牌や骨壷・遺影などをお祀りして供養します。祭壇や仏具セットは葬儀のプランに含まれていることが多く、葬儀社が準備してくれることがほとんどです。含まれていない場合は、仏具店などで自分で準備してお祀りします。
葬儀は終わってからもやるべきことが多いため、心身が疲弊する時期です。体調を優先しながら少しずつ取り組むとよいでしょう。
葬儀から1週間後以降
葬儀の後処理が終わったら、49日法要の手配などを進めていきます。
- 法要の手配(参列者への案内、僧侶の手配、会食の手配など)
- お墓、納骨の手配
- 仏壇・位牌・卒塔婆などの準備
- 香典の手配など
日程調整や会場の予約が必要な法要の手配や、作成に日数が必要な位牌・卒塔婆などの準備は早めに取り組むと良いでしょう。死後に必要な手続きも、期日を確認しながら進めます。
お墓がある場合は、追加の彫刻などの手配が必要です。お墓がない場合は49日の納骨が間に合わない場合もあるので、納骨法要を49日以降にし、お墓の手配を進めましょう。
遺品整理も、できるだけ早く取り組むのがおすすめです。
49日法要当日
49日当日は、法要や納骨・忌明けの会食などがおこなわれます。仮位牌から本位牌(黒い位牌)に変える儀式も同じタイミングです。
お墓があり納骨できる場合は一般的に、49日法要と一緒に納骨をします。法要の後は、集まった親族や参列者とともに、故人を偲びながら会食をおこないます。
49日の法要を終えると忌明けとされ、遺族が喪に服す期間もこの日で終了です。
49日以降(忌明け)
49日以降は、香典返しや形見分けをおこないます。葬儀に来ていただいた場合は当日に香典返しをお渡しすることがほとんどですが、お渡しできなかった場合や葬儀以外で香典をいただいた場合の香典返しは、忌明けのタイミングとなります。事前にリストを準備しておき、忌明け後に送付しましょう。
遺品整理が終わっている場合は、49日や忌明けのタイミングで形見分けをする人が多いです。
49日までにおこなう供養

仏教では、7日ごとに故人が極楽浄土に行けるようにと祈る忌日法要(追善供養)をおこないます。49日までに6回の供養があり、それぞれ生前のおこないへの審判を受けながら冥土への実を進み、49日に最終審判を受けるとされています。
| 名称 | 命日からの日数 |
|---|---|
| 初七日(しょなのか) | 7日目 |
| 二七日(ふたなのか) | 14日目 |
| 三七日(みなのか) | 21日目 |
| 四七日(よなのか) | 28日目 |
| 五七日(いつなのか) | 35日目 |
| 六七日(むなのか) | 42日目 |
近年は葬儀と同時もしくは葬儀後に初七日の供養をおこない、二七日〜六七日までの供養を省略して49日の法要のみで済ませることが増えています。
忌中と喪中の違い

忌中は故人の冥福を祈る期間で、49日までが一般的です。神道の場合は50日になります。忌中期間は基本的に自宅で静かに過ごし、故人の供養をおこなう期間です。祝い事やレジャーなどは基本的に避けるべきとされています。
一方、喪中は故人を偲び喪に服す期間で、故人との関係や地域によって変わります。一般的には二親等の家族までが該当し、それ以外は喪中としないことがほとんどです。長くても一周忌までで、喪明け後は日常生活に戻るとされています。
故人との関係性と喪中の期間は、次のとおりです。
| 故人との関係性 | 喪中の期間 |
|---|---|
| 父母や養父母・義父母 | 1年 |
| 配偶者・子ども | 1年 |
| 祖父母 | 3〜6ヵ月 |
| 兄弟姉妹 | 1〜3ヵ月 |
喪中期間は宗教によって変わることもあるため、葬儀などの際に僧侶に確認しておくと安心です。
49日までにおこなうこと5つ
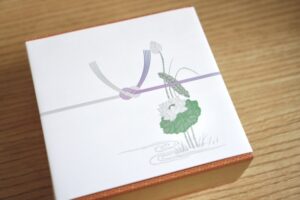
49日までに遺族がおこなわなければいけないことは、主に以下の5つです。
- 49日法要の準備
- 香典返しの手配
- 位牌や仏壇の購入
- 遺品整理
- 死亡後の手続き
詳しく見ていきましょう。
49日の準備
忌明けとなる49日法要の準備は時間がかかるものもあるので、早めに進めていきます。日程を決め参列者に案内を出したり、法要の会場や会食の手配、僧侶の手配をしたりなど多岐にわたるため、抜けや漏れがないよう確認しながら進めます。場合によっては卒塔婆の準備や墓石への名入れなどが必要になる場合もあるので、何が必要かあらかじめ調べてリストにしておきましょう。
日程は僧侶と相談のうえ、会場と合わせて手配します。参列者への案内は早めに出し、人数に合わせて会場や会食の手配を進めましょう。
【49日法要の準備リスト】
- 法要の日程や会場の決定
- 僧侶の手配
- 参列者への案内状の送付
- 会場・会食の手配
- お布施やお車料の用意
- お供物などの準備物の用意
- 墓石への名入れ
- 卒塔婆の手配
準備物は宗教・宗派によって変わることもあります。事前に僧侶に尋ねておくと、スムーズに進められるでしょう。
香典返しの手配
49日の法要に参列してくださった人への返礼品や、忌明けの香典返しの準備をおこないます。香典をいただいた人をリストにし、金額にふさわしい品を用意するのが慣例です。
リストの準備やお返しする品物を選ぶのは意外と時間がかかるため、早めに取りかかるのがおすすめです。手配は葬儀社や百貨店、ギフト専門店などでおこないます。最近は通販などでも準備できます。挨拶状やのし・手提げ袋など、必要なサービスがついているところに依頼するとスムーズに用意できるでしょう。
位牌や仏壇の購入
49日の法要が終わると、自宅に仏壇を設置してお祀りします。自宅に仏壇がない場合は仏壇の購入、および位牌の手配が必要です。宗教や宗派によって細かな違いがあるため、法要を執りおこなってくれた僧侶などに確認しながら手配しましょう。
位牌の準備には、日数がかかる場合があります。手配が直前になると49日に間に合わない場合も考えられるため、法要などの準備と合わせて、早めに済ませておきましょう。新しく仏壇を準備した場合は、開眼供養(魂入れ)が必要なことがほとんどです。宗教や宗派によって必要な儀式が異なるため、事前に菩提寺に確認しておきましょう。
遺品整理
49日は親族が揃うため、一般的にはこの日に形見分けをおこないます。形見分けをおこなうためには故人の部屋や家を片付ける必要があるため、49日に間に合うように早めに着手しましょう。
賃貸などで故人が住んでいた家を引き払う必要がある場合は、遺品整理業者に依頼するのもおすすめです。特に、遺品が多すぎる場合や孤独死など特殊な状態で亡くなった場合は、自分で片付けるのは難しいことがほとんどです。早めにプロに依頼し、できるだけ短期間で片付けるとよいでしょう。
死亡後の手続き
死亡後にしなければならない手続きも、順次進めていきましょう。期限が決まっている手続きも多いので、すべきことをリスト化して期限の短いものから取り組むのがおすすめです。
死後に必要となる主な手続きは、以下のとおりです。
- 国民健康保険や年金などの手続き
- 電気やガス、携帯などの解約手続き
- 免許証などの返却
- 年金や社会保険などで受け取れる費用の手続き
- 預貯金の払い戻し、名義変更
- 保険金などの手続き
ただし、相続放棄などを予定している場合は、遺品整理や死亡後の手続きは慎重に進める必要があります。詳しくは「相続放棄する場合の家の片付け方を徹底解説!してもよいことやいけないこと・よくある疑問も紹介」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
49日まで遺族が控えること
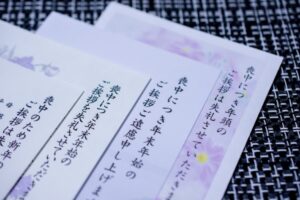
49日までの忌中と呼ばれる期間は、故人を偲び供養に専念するための期間と考えられており、祝い事などは控えるべきとされています。とくに、以下の8つは控えるようにしましょう。
- 年始の挨拶
- 入籍や結婚式
- 祝い事
- 神社への参拝
- 旅行やレジャー
- 引越や新築・リフォームなど
- 神棚へのお参り
- お歳暮やお中元
ひとつずつ説明します。
年始の挨拶
忌中や喪中の間は年賀状の送付や新年の挨拶回り、新年会への参加などは控えましょう。喪中におめでたい雰囲気を出すのは避けるべきという古くからの慣習があるためです。
年賀状の代わりとしては、喪中ハガキを出すのが通例です。喪中ハガキが出せなかったときは、寒中見舞いでお知らせしましょう。
年始の挨拶は「おめでとう」の言葉を避け「よろしくお願いします」などとすれば問題ありません。お年玉をあげるときもマナーが決められており、ポチ袋を使わずにお小遣いとして渡すと良いでしょう。
入籍や結婚式
忌中に予定していた入籍や結婚式も、可能であれば延期するのが望ましいです。延期するかどうかは、両家で相談してから決めると良いでしょう。
とくに神前式を予定している場合は、事前にお祓いなどを受けておく必要があります。故人が楽しみにしていた場合や、日数的に延期が難しい場合などは予定通りおこなうこともありますが、両家でよく相談しながら進めましょう。
祝い事
忌中の間は、祝い事全般を避けるのが慣例です。避けたほうが良いとされている祝い事は、以下のとおりです。
- 慶事への参加
- 結婚式などへの参列
- 七五三、祝賀会などへの参加など
正月の飾り付けなども、忌中や喪中の間は避けるとされています。
一方で、七五三など子どもへの祝い事についてはお祝いを贈ることは問題ないとされることが増えています。しかし、忌中にお祝いを贈ると先方に気を遣わせることもあるため、忌明けを待って贈るとよいでしょう。
神社への参拝
忌中の間は穢れが残っているとされるため、神社への参拝は控えましょう。49日が過ぎ忌中が明けた後は参拝しても問題ありませんが、喪中の間は脇道から入るなど配慮が求められることもあります。どうしても忌中期間に参拝が必要な場合は、忌明け祓いを受けてください。
厳格な神社などでは、喪中の期間でも参拝を控えて欲しいと言われることもあります。一般的なお参りなら問題ないことがほとんどですが、気になる場合は事前に問い合わせておくと安心です。
旅行やレジャー
忌明けまでは旅行やレジャーなどをできるだけ控えて、静かに過ごす時期です。外出は最低限にし、自宅で体調を整えながら個人を偲ぶとよいでしょう。納骨までは故人の遺骨も自宅でお祀りするため、長期間留守にすることは、できるだけ避けるのが慣例です。
どうしても日程が調整できない場合や、故人との関係性によっては、忌中でも旅行への参加は問題ないと考えるケースもあります。遺族によって判断はさまざまなので、近親者に相談しながら延期するかどうかを判断しましょう。
忌中はしなければならないことも多く、まだ故人を喪った悲しみも癒えていない時期なので、旅行やレジャーを楽しむ気持ちにもなれないことがほとんどです。葬儀後のさまざまな手続きが終わり、忌明け後の落ち着いた時期に改めるとよいでしょう。
引越しや新築・リフォームなど
忌中は大きな買い物は避けるほうがよいとされているため、引越しや新築・リフォームなども避けることが一般的です。とくに新築は地鎮祭など神事をおこなうため、喪中の間は避ける必要があります。
地鎮祭などすでに予定されており延期が難しい神事は、神式でなく仏式で執りおこなう、お祓いを受けるなどの方法で延期を回避できます。故人との関係性によってはそこまで気にしないケースもあるため、親族と相談しながら進めてください。
神棚へのお参り
家族が亡くなった場合は、自宅の神棚へのお参りも忌中の間は避けます。神棚は半紙を貼って神棚封じをおこない、毎日のお祀りは遠慮しましょう。
神棚封じは、故人と同居していた人以外の人がおこなうのが慣例です。神殿は閉じ、お供え物などは下げておきます。忌中期間は神棚を封じたままにしておき、忌中が開けたら半紙を外して神殿を開け、掃除をした後に榊や水・酒などの供物をし、お参りしましょう。
神棚の封じ方や解き方は宗教や宗派によって異なることがあるため、菩提寺などに確認してからおこなうと安心です。
お歳暮やお中元
お歳暮やお中元も、忌中の間は贈らないのがマナーとされています。相手が忌中の場合も贈らないようにし、忌明けに手配するようにしましょう。どうしても忌中の間に贈りたい場合は、紅白の水引を使わないようにするなどの配慮をしたうえで手配します。
忌明けにお歳暮やお中元を手配した場合、本来贈るべき時期からずれてしまうことがあります。その場合は、お中元なら暑中見舞いや残暑見舞いとして、お歳暮なら寒中見舞いとして贈れば問題ありません。お歳暮やお中元を忌中ではなく喪中に送る場合は問題ありませんが、気になる場合は水引を使わず、シンプルな包装紙に包んで贈るとよいでしょう。
49日までの過ごし方についての注意点

49日までの過ごし方については、以下の4つに注意してください。
- 忌明けまではできるだけ家で過ごす
- 法要の準備は早めに進める
- 家族や親族と相談しながら進める
- 期限が決まっている手続きに注意する
順番に説明します。
忌明けまではできるだけ家で過ごす
忌中期間は、故人を亡くしたばかりで体調を崩しやすい時期です。故人を悼みながら静かに過ごし、外出などは最低限するのがおすすめです。通勤や通学、日常生活に必要な活動のみにして外出やレジャーは慎み、49日の法要に向けて体調を整えておきましょう。
特に葬儀後は慌ただしい日々が続くため、気を張っていて疲れを感じにくく、体調が悪いことにも気付きにくいです。慌ただしさが落ち着いた頃に悲しみや疲れが押し寄せてきます。
また、49日までは7日ごとに忌日法要もあるので、できるだけ自宅で過ごし、故人に思いを寄せるのがよいでしょう。
法要の準備は早めに進める
49日法要に必要な手続きや準備は想像以上に多いので、早めに取り組むのがおすすめです。とくに、香典返しの手配や位牌・墓石の準備などは時間がかかります。また、49日に形見分けを予定している場合は遺品整理なども急ぐ必要があります。
やるべきことが多く、あっという間に49日が来てしまうため、リストにして抜けや漏れがないか確認しながら進めましょう。
家族や親族と相談しながら進める
忌中はしてはいけないこと、すべきことが多いので、わからないことは家族や親族と相談しながらおこなうようにしてください。昔は禁止されていたことも、現代ではあまり気にせずおこなえる場合があります。故人との関係性や地域でも大きく変わるので、その都度、家族や親族と相談しながら進めるとよいでしょう。
不安なことやわからないことがあるときは家族や親族、菩提寺などに相談しながら進めると安心です。
期限が決まっている手続きに注意する
忌中にすべきことは意外と多く、忙しい日々となります。死後の手続きや法要・お墓の手続きなど、期限が決まっているものは早めに取り組み、忘れないように気をつけましょう。体や心を休める暇もなくさまざまな手続きをしなければならないため、必要な手続きをうっかり忘れてしまうことも少なくありません。
中には期限までに手続きできないと困る手続きもあるため、あらかじめやるべきことをリストアップし、期限を確認したうえで順番に取り組むとよいでしょう。法要の準備だけでなく、相続などの手続きも早めに確認しておくと安心です。
49日までに起こる事まとめ

49日までは忌中期間といい、故人の供養に専念するのが慣例です。故人が極楽浄土に行けるように祈る忌日供養(追善供養)が7日ごとにおこなわれ、静かに故人の死を悼んで過ごします。また、49日の法要の準備や死後の後処理・相続などの手続きを期日内に進めなければなりません。位牌や墓石の準備など、時間のかかるものもあるため、できるだけ早めに取りかかりましょう。
49日までの忌中期間は、遺族は年末年始の挨拶や入籍、結婚式など、多くの行事が控えるべきこととされています。
しかし、現代においては昔ほど厳しくなく、故人との関係性によっては問題なくおこなえる行事もあります。そのため、他の家族や親族、関係者の方と相談したうえでご自身にとって納得のいく形で決めると良いでしょう。
また、忌中期間に遺品整理をおこなうときは、専門業者に依頼するのがおすすめです。深い悲しみの中で遺品整理をするのは難しく、すべきことも多いのでゆっくり時間を取れないことも少なくありません。
タイヨーが提供しているサービス「遺品整理みらいへ」では、特殊清掃を始め遺品整理や片付けのお手伝いまで、ご遺族の状況に応じたお手伝いを承っております。ご事情を伺いながらお手伝いさせていただきますので、急いで部屋を引き払わなければならないなど、お困りごとがありましたらぜひ電話・メール・LINEにて、お気軽にご相談ください。







